社会人になると、仕事の節目やチームの雰囲気作りのために、さまざまな「飲み会の名称」が登場しますよね。「え、これってどういう意味?」「いつ開催されるの?」と疑問に思ったことがある人も多いはず。この記事では、定番からややマイナーなものまで、よく使われる飲み会の名称をひとつずつ解説していきます。実際の会社やサークルでもそのまま使われる言葉ばかりなので、覚えておくと会話がスムーズになりますよ!
決起会(けっきかい)

決起会は「これから頑張っていこう!」という気持ちを共有するために開催される飲み会です。新しいプロジェクトが始まる前や、新年度がスタートしたタイミングでよく行われます。モチベーションをみんなで上げる場なので、雰囲気はポジティブで明るいことが多いです。
私の前職でも、年度初めに必ず決起会がありました。一次会では部長が「今年は◯◯を達成しよう!」と乾杯の挨拶をし、現場全体で目標を共有する時間に。その後は席を移動しながらメンバー同士で「今年もよろしく!」と声を掛け合うのが恒例でした。
ちなみに決起会は、事前に簡単な目標発表が行われることもあります。たとえば営業チームなら「今年の目標は◯件契約!」のようなもの。参加者みんなで前向きな空気を作る場なので、ネガティブな話題はできるだけ避けると良いでしょう。
納涼会(のうりょうかい)
納涼会は「暑さを楽しみながら癒す飲み会」です。開催されるのは主に夏。社内でクーラーの効いた居酒屋もいいですが、屋外のビアガーデンやテラス席で行われることも多く、雰囲気がとても爽やかです。
たとえば私が以前参加した納涼会では、屋上ビアガーデンで冷えたビールと焼き物を囲みながら「夏ってやっぱいいな~!」とみんなで語りました。仕事の話も多少はしますが、どちらかというと雑談が中心で、リラックスして仲を深められる場という印象です。
服装もややカジュアル寄りでOKな場合が多いので、形式張った飲み会が苦手な人にも向いています。
納会(のうかい)
納会は「一年の締め」に行われる飲み会や会合のことです。年末、仕事納めのタイミングで実施されることが多いのが特徴です。会社全体、部署単位、チーム単位など規模はさまざまですが、共通しているのは「今年もお疲れさまでした!」という感謝の雰囲気。
私のときは、最後に必ず「一年間の振り返り」が行われていました。上司からの総括、チームの成果の共有、そして締めの一本締め。飲み会というよりも、儀式的な意味も強い場と言えるかもしれません。
堅い会に見えますが、二次会からは一気に開放モードになることも多いです。
忘新年会(ぼうしんねんかい)
忘年会と新年会をまとめた言い方が「忘新年会」。年末か年始、または両方の時期に行われるお祝いムード満点の飲み会です。「今年の疲れを忘れよう!」と「来年もよろしく!」の両方の意味を持つため、特に盛り上がりやすいのが特徴です。
居酒屋では忘年会シーズンのコースが用意されるので、予約が必要なことがほとんど。ビンゴゲームや景品がついたイベント系忘年会もよくあります。私の会社では新入りが余興担当になることが多く、ダンスや漫才を披露することも…(今思うと、あれはなかなか大変でした)。
慰労会(いろうかい)
慰労会は「お疲れさま!よく頑張ったね!」という気持ちを共有する飲み会です。プロジェクト完了後や、繁忙期を乗り越えたあとに開かれることが多いです。形式としてはリラックスした雰囲気が多く、みんなでほっと一息つくような空気が流れます。
以前、長期案件が終わったあとに開催された慰労会では、普段はクールな先輩が「実はあの時めっちゃ焦ってた」と裏話をしてくれて、意外な一面を知れました。達成感と安心感が混ざった、心地よい飲み会です。
打ち上げ(うちあげ)
打ち上げは、イベントや制作物などが無事に終了したときに行う飲み会です。学生時代の文化祭、社会人の展示会、スポーツ大会のあとなど、幅広い場面で使われる名前です。
打ち上げは気持ちが明るく、盛り上がりやすいのが特徴。「お疲れー!」と乾杯しながら、思い出話や裏話がどんどん出てきます。私が大学時代に参加したサークルの打ち上げでは、失敗談で爆笑したり、次回のイベントのアイデアが自然に出てきたりと、一番好きなタイプの飲み会でした。
歓迎会(かんげいかい)
歓迎会は、新しく仲間になった人を迎えるための飲み会です。新入社員や中途入社、異動で新しく配属された社員など、「これからよろしく!」という気持ちを伝える大切な場です。雰囲気としては、優しい空気・会話の多い空気が生まれやすく、「まずは馴染んでもらおう」という配慮が働きやすい会でもあります。
私が新入社員のとき、先輩が「緊張すると思うけど、ここは仕事の話より気軽な場だからね」とあえて柔らかく接してくれたことを今でも覚えています。話題は出身地や趣味などが中心で、仕事の細かい話はあまりしません。歓迎会での第一印象が、その後の人間関係をいい意味で支えてくれることだってよくあるんです。
また、歓迎会では「新入りが自己紹介をする」時間が設けられることも多いので、話す内容をあらかじめ軽く準備しておくと安心です。「趣味」「好きな食べ物」「休日の過ごし方」など、砕けた話題でOK。変に作り込む必要はありませんが、笑顔で話せるとより好印象です。
送別会(そうべつかい)
送別会は、異動や退職、卒業などでその場を離れる人を見送るための飲み会です。「今までありがとう」「新しい場所でも頑張ってね」という気持ちが込められています。飲み会の中でも特に感情が動きやすい会で、しんみりする場面があるのが特徴です。
私が以前参加した送別会では、退職する先輩に向けて、チーム全員からメッセージカードを渡しました。その先輩は普段クールで淡々としていた方でしたが、その時は思わず涙しており、場に居た全員がなんとも言えない温かい空気に包まれました。
送別会では、記念品を用意したり、思い出話が語られたり、最後に締めの挨拶が入ることが多いです。笑って送り出すタイプの送別会もあれば、少し感傷的になる送別会もあります。いずれにせよ「ありがとう」を伝える大切な時間です。
親睦会(しんぼくかい)
親睦会は、人と人との距離を縮めるために開催する飲み会です。会社だけでなく、地域団体・趣味サークル・学校の保護者会など、さまざまな場所で使われる名称です。目的は「仲良くなること」なので、堅苦しさは比較的少なめ。
私が経験した親睦会の中では、カードゲームや簡単なレクリエーションを取り入れるものもありました。特に学生サークルだと、「アイスブレイク」的なゲームで笑いが起きて、その後ぐっと話しやすくなることが多いです。
仕事の親睦会であれば、「普段あまり話さない他部署の人と交流できる」メリットも大きいです。普段の業務では接点が少なく、声を掛けづらい相手でも、飲み会という場があるだけで一気に距離が縮まります。結果として、仕事がスムーズになることもあります。
懇親会(こんしんかい)
懇親会は親睦会に似ていますが、より「交流の質」を重視した飲み会です。業界団体、学会、ビジネスセミナーなど、立場や所属の異なる人が集まる場面で行われることも多いです。名刺交換のようなビジネス的な要素が含まれることもあるので、親睦会よりややフォーマルな印象があります。
私が参加したセミナー後の懇親会では、まさに「情報交換の場」という雰囲気でした。仕事への取り組み方、新しいアイデア、業界の話など、「ためになる話題」が自然と出てきます。お酒の席ではあるものの、ビジネス上の出会いが次の仕事につながる場合もあります。
ただし、あまり堅くなりすぎず、「まずは楽しく話すこと」が基本。相手へのリスペクトさえ忘れなければ、むしろ自然体のほうが信頼されます。
まとめ:シーンに合わせて飲み会の名称を使い分けよう
飲み会の名称には、ただ集まって飲むだけではなく、それぞれに明確な“意味”や“気持ち”が込められています。「頑張ろう」「お疲れさま」「ようこそ」「ありがとう」「仲良くなろう」。こうした言葉を、場にあわせて自然に伝えるための名前なのです。
名称を正しく理解することで、雰囲気作りや立ち振る舞いも変わり、より気持ちよく場を共有できます。仕事でもプライベートでも使える知識なので、ぜひ覚えておいてくださいね。
次に飲み会が開かれたとき、「あ、これは◯◯会だな」とわかるだけで、ちょっとだけ大人になった気分が味わえるはずです。
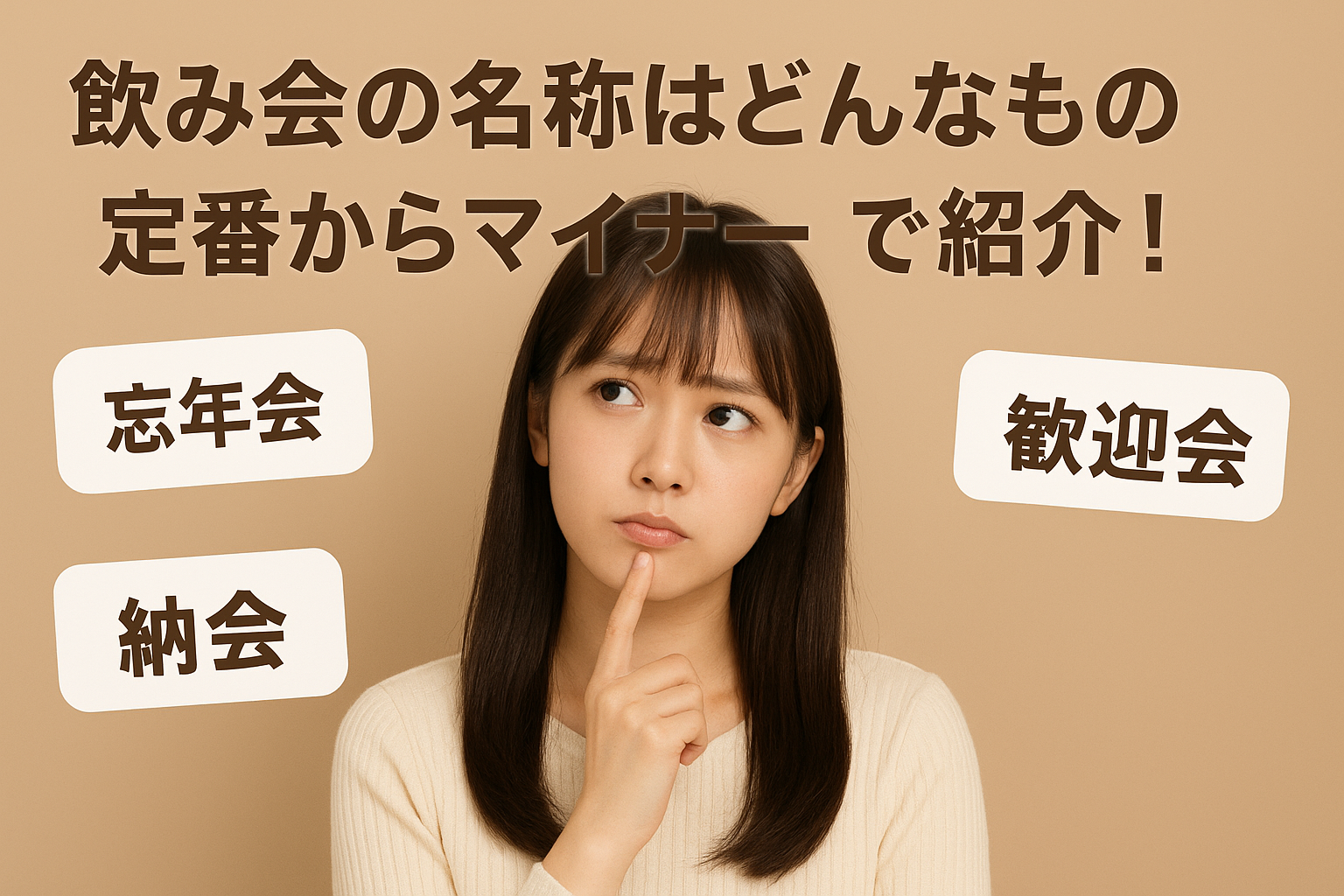


コメント