「居酒屋を開業したものの、思ったより利益が出ない」「儲かるメニューが知りたい」──そんな悩みを持つ飲食店オーナーは少なくありません。
実際、メニュー選びひとつで居酒屋の利益は大きく左右されます。私は以前、都内の個人経営居酒屋でスタッフとして働いていましたが、儲かるメニューを工夫することで、月の利益が数十万円単位で改善された経験があります。
この記事では、居酒屋の収益を支える「儲かるメニュー」について、原価率・利益率の実例や現場での体験談を交えながら詳しく解説します。これから居酒屋を始めたい方、今の経営を見直したい方は必見です。
儲かる居酒屋メニューの共通点とは?
居酒屋で利益が出るメニューにはいくつかの共通点があります。
- 原価率が低い(20~30%台)
- オペレーションが簡単で提供が早い
- まとめて仕入れてロスが出にくい
- 定番メニューで注文されやすい
- ドリンクと相性が良い(回転率が上がる)
この条件を満たすメニューを戦略的に導入することで、1品あたりの利益を最大化できます。
儲かるメニューの利益率一覧【定番&高利益メニュー表】
ここでは、私が実際に勤務していた居酒屋でも「よく出て、かつ儲かったメニュー」を中心に、原価率や利益率をまとめた表を紹介します。
| メニュー | 販売価格 | 食材原価 | 原価率 | 粗利益 |
|---|---|---|---|---|
| ポテトフライ | 480円 | 80円 | 16.7% | 400円 |
| 枝豆 | 390円 | 60円 | 15.3% | 330円 |
| 鶏の唐揚げ | 680円 | 180円 | 26.4% | 500円 |
| 出汁巻き玉子 | 580円 | 120円 | 20.7% | 460円 |
| 焼き鳥(5本盛り) | 780円 | 240円 | 30.8% | 540円 |
| もつ煮込み | 620円 | 130円 | 21.0% | 490円 |
この表からもわかるように、居酒屋で儲かるメニューは調理工程が単純で、原価率が20~30%程度に抑えられているのが特徴です。
実際に「儲かった」と感じたメニューと理由
● ポテトフライは居酒屋の最強利益商品
私が働いていた店で断トツの利益商品がポテトフライでした。冷凍ポテトを揚げるだけなので、オペレーションは1分程度。1日に30~50食出るので、粗利だけで1万円を超える日もざらにありました。
● もつ煮込みは仕込み型で回転が早い
もつ煮込みは大量仕込みに向いており、味も日持ちするためロスが少なく、利益率が高かったです。1人前の食材原価が100円台前半なのに、提供価格は600円前後。味がしっかりしていて、お酒が進むメニューのためドリンク注文も増えます。
● 出汁巻き玉子は「手作り感」で価値アップ
原価は安いですが、焼きたてで提供することで「手作りの丁寧な居酒屋」の印象を与えることができました。焼く手間はかかりますが、出すたびに「うまい」と言ってもらえた人気メニューで、リピーターにもつながりやすかったです。
体験談:失敗した「儲かりそうで儲からなかったメニュー」
逆に、原価率が高く利益を圧迫したメニューもありました。
- 刺身盛り合わせ:ロス率が高く、仕入れ価格が天候に左右される
- アボカド系メニュー:熟しすぎ・固すぎでロスが頻発
- 手の込んだ創作料理:提供に時間がかかり、回転率が落ちる
とくに刺身系は、見た目や品質を保つために常に新しいネタを仕入れる必要があり、ロスと原価のリスクが高いです。個人店では慎重に導入した方が良いと感じました。
儲かるメニューを作る3つのポイント
では、どのようにして「儲かるメニュー」を構築すればよいのでしょうか?
① 原価率25%以下を基準に設計する
目安としては、原価率は25%以下が理想。30%を超えると他の経費(人件費・光熱費など)を差し引いたときに手元に残りにくくなります。
② 食材の使い回しができるようにする
例えば「鶏もも肉」は唐揚げ・焼き鳥・チキン南蛮など複数メニューに転用可能。仕入れ量を増やしてコストを下げつつ、無駄を減らせます。
③ 調理工程をシンプルにする
提供までに時間がかかると、回転率が下がり売上も低下します。冷凍や下ごしらえ済みの素材を活用して、オペレーション効率も重視しましょう。
儲からないメニューの特徴と避けるべきポイント
居酒屋で「儲かりそうに見えて実は利益が出にくいメニュー」も存在します。これらは、オペレーションや原価の問題で利益を圧迫する可能性が高いため注意が必要です。
● 原価が高く、注文数が少ない
たとえば高級肉を使ったステーキや、ウニ・イクラなどの高級食材系は一見魅力的ですが、原価率が高く、回転も悪いため経営を圧迫します。
● 廃棄リスクが高いメニュー
刺身や生野菜などのナマモノ系は賞味期限が短く、天候や仕入れで原価がぶれやすいため注意。廃棄が続くと大きな損失に直結します。
● 提供に時間がかかる手間メニュー
煮込み系やオーブン料理など、提供まで10分以上かかるような料理は回転率を下げる原因になります。厨房が混乱し、顧客満足度の低下にもつながりやすいです。
ドリンクで利益を出す!売れる仕組みの作り方
飲食店、特に居酒屋ではドリンクメニューが利益の柱となるケースがほとんどです。
● ドリンク原価率の目安
| ドリンク | 販売価格 | 原価 | 原価率 |
|---|---|---|---|
| 生ビール(中ジョッキ) | 580円 | 120円 | 20.7% |
| ハイボール | 480円 | 80円 | 16.7% |
| サワー各種 | 450円 | 70円 | 15.5% |
| ソフトドリンク | 350円 | 40円 | 11.4% |
ドリンクは原価率10~20%程度が基本です。特にサワーやハイボールなどの炭酸系はコスパがよく、まとめて仕込むことで手間も最小限に抑えられます。
● お通しの工夫で利益をプラス
お通しは単価が300円前後でも、1日30人分出れば9,000円、月に換算すると20万円以上の追加売上につながります。内容は簡単な小鉢(煮物や和え物など)で十分ですが、「ちゃんと手作り感があるもの」が満足度を上げるポイントです。
● 飲み放題は「制限・管理」がカギ
飲み放題は集客の武器になりますが、条件設定をしないと原価が跳ね上がり赤字になります。時間制(90分)+ラストオーダー+対象ドリンク限定、を徹底して利益を確保しましょう。
心理的に「売れる」メニュー表の作り方
お客様の選択行動を誘導することで、自然と利益率の高いメニューを選ばせることができます。以下はそのテクニックの一部です。
● 視線誘導:目立つ位置に高利益商品を配置
メニュー表の左上 or 中央に「おすすめ」「人気No.1」などのPOPをつけて高利益商品を配置しましょう。心理的に視線が最初に集まりやすい場所にあると、注文率が上がります。
● セット・盛り合わせで単価アップ
「唐揚げ+ポテトセット」や「晩酌セット(ドリンク+おつまみ2品)」などは単品よりお得感を出しつつ、原価を抑えられる工夫です。結果的に1人あたりの単価アップにもつながります。
● 写真のクオリティで売上が変わる
写真付きメニューは特に大事です。スマホで撮った簡易な画像よりも、照明や盛り付けにこだわった高品質写真を使うだけで、注文率が1.5倍~2倍になることもあります。
最近のトレンドメニューと売れ筋アイデア
競合と差別化を図るには、少し流行を取り入れたメニューも効果的です。特にSNS映えを意識した以下のような商品が話題になりやすいです。
- 韓国風チーズメニュー(チーズボール・チーズタッカルビ)
- 映えドリンク(カラフルなサワー・光るグラス)
- 串焼きの創作アレンジ(バジル、トマト、クリームチーズ)
- スパイス系(山椒唐揚げ、スパイシー枝豆)
- ビーガン・グルテンフリー対応(健康志向層の取り込み)
ただし、導入の際は仕入れやオペレーションに負担が出ないかを事前に検証しましょう。トレンド商品は「期間限定」で投入し、様子を見ながら定番化するのが効果的です。
FAQ:よくある質問
Q. 原価率はどのくらいが理想ですか?
A. フードメニューで25~30%、ドリンクで15~20%が目安です。全体として原価率30%以下を目指すと利益が出やすくなります。
Q. おすすめのドリンクメニューは?
A. ハイボールやサワー系は原価が安く、注文数も多いためおすすめ。さらに「味変」や「変わり種フレーバー」で飽きさせない工夫を加えると売上が伸びます。
Q. メニュー開発で失敗しないコツは?
A. まずは原価の安い素材で試作し、従業員や常連客に試食してもらうところから始めると無駄がありません。仕入れが安定する素材を選びましょう。
まとめ:儲かるメニューを知れば居酒屋経営は安定する
居酒屋経営で成功するには、「儲かるメニュー」の構築が何よりも重要です。
- 原価率の低いフード・ドリンクを中心に構成する
- 調理・提供がスピーディーで、ロスが少ない
- セットメニューや視線誘導で単価を上げる
- 流行やニーズを適度に取り入れる
私が現場で体験したように、小さな工夫の積み重ねが利益を大きく左右します。
まずは一つでも良いので、今あるメニューの中から「もっと儲かる形に改良できるか?」を見直してみてください。
居酒屋経営は苦しいときもありますが、やり方次第でしっかり利益を出すことが可能です。ぜひ本記事を参考に、儲かるメニュー作りにチャレンジしてみてください。

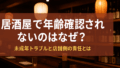
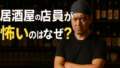
コメント