「最近の若手は飲み会に来ない」「参加しないと印象が悪いのでは?」──そんな声を聞いたことはありませんか?
かつては仕事の延長線とされていた“飲み会”も、今や価値観が大きく変わってきています。
そこで今回は、飲み会に来ない人の印象、現代社会における飲み会の位置づけ、そして昔との考え方の違いについて、私自身の体験談や実例を交えて詳しくご紹介していきます。
昔の職場での飲み会の位置づけ
まず初めに飲み会の位置付けですが、かつての日本社会では、飲み会は「仕事の一部」として扱われていました。
上司との関係づくりやチームの結束を強める“重要な場”とされ、参加するのが当然という文化が根付いていたのです。
特に昭和〜平成初期の時代は、仕事が終わると「とりあえず一杯!」が合言葉。
飲みニケーション(飲み+コミュニケーション)という言葉も生まれ、職場の信頼関係は居酒屋で築かれるものだと考えられていました。
「あの頃は飲み会でしか本音を話せなかった」という50代男性の声も。
つまり、昔の職場では“参加しない=協調性がない”という印象を持たれることも多く、
飲み会に出ることが「仕事ができる人」の条件の一つとすらされていたのです。
| 時代 | 飲み会の位置づけ | 主な目的 |
|---|---|---|
| 昭和〜平成初期 | 半ば義務的な社交場 | 上司との関係づくり、結束強化 |
| 令和以降 | 自由参加・リフレッシュ目的 | 交流・気分転換・情報交換 |
現代では「行かない=悪印象」とは限らない
現代の職場では、「飲み会に参加しない=印象が悪い」という考え方は薄れています。
特にZ世代やミレニアル世代の間では、「仕事とプライベートを分けたい」「お酒が苦手」「休日は自分の時間を大切にしたい」という価値観が主流です。
上司や人事の意識も変化しており、
「強制参加はパワハラになる可能性がある」
「無理に来てもらっても気を遣わせてしまうだけ」
といった考え方が広がっています。
つまり、今の時代では「行かない理由」よりも「普段の仕事ぶり」が評価の軸になっているのです。
実際に20代会社員の声を聞いてみると、
「仕事が終わった後はリセットしたい。飲み会に行かなくても、日常でちゃんと話せていれば問題ないと思う」
という意見が多く見られました。
飲み会に行かない人の印象【良い・悪いの両面】
では、実際に「飲み会に来ない人」はどう見られているのでしょうか?
ここでは、ポジティブ・ネガティブ両方の視点から見てみましょう。
良い印象
- 自分の考えを持っていてブレない
- 仕事とプライベートをしっかり分けている
- お酒に流されず冷静
悪い印象
- 付き合いが悪い・冷たい
- 協調性がないように見える
- 本音を話さない人と思われる
とはいえ、日頃の人間関係や仕事への姿勢がしっかりしていれば、印象が悪くなることはほとんどありません。
むしろ、毎回無理に参加して不機嫌そうにしているよりも、
「参加しないけど、日中は明るく接している人」のほうが印象は良い場合も多いのです。
飲み会に参加しないときの上手な断り方
とはいえ、全く説明せずに欠席を続けてしまうと、「なぜ来ないのか」と誤解されることも。
そこで、角が立たない断り方をいくつか紹介します。
- 「今日は家族の予定がありまして、また次回お願いします!」
- 「最近お酒を控えているので、また飲み会以外の機会にご一緒させてください」
- 「体調管理を優先したいので、今回はパスさせていただきます」
ポイントは、“行きたくない”ではなく“別の理由がある”と伝えること。
また、後日ちょっとしたお礼や会話を交わすことで、人間関係を良好に保つことができます。
実際に筆者も、飲み会に参加しなかった際に「いつもありがとうございます、昨日盛り上がったみたいですね!」と笑顔で話しかけたところ、むしろ印象が良くなった経験があります😊
リモート時代の“オンライン飲み会”という選択肢
コロナ禍以降、急速に広まった「オンライン飲み会」も注目されています。
自宅から気軽に参加できるため、移動や時間の拘束がなく、
「飲み会の雰囲気は好きだけど外出は面倒」という人にもぴったりです。
企業によっては、チームのコミュニケーション強化のために月1回オンラインで軽く乾杯するところも。
こうした形なら、参加のハードルもぐっと下がります。
| 形式 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 対面飲み会 | 直接話せて関係が深まりやすい | 時間拘束・費用負担が大きい |
| オンライン飲み会 | 手軽・移動不要・家庭との両立がしやすい | 会話のテンポが難しい |
昔と今の“飲み会観”の違い
昔は「上司との飲み会=仕事の一部」、今は「個人の自由」。
この変化の背景には、働き方や価値観の多様化があります。
- 仕事とプライベートの線引きを大切にする
- アルコールに頼らず人間関係を築く
- コミュニケーションの場が多様化(カフェ・ランチ・オンラインなど)
つまり、「飲み会に行かない」=「関係を拒絶している」ではなく、「自分に合った方法でつながりを持ちたい」という考えが主流になっているのです。
企業側もその変化を理解し、「参加しなくても評価に影響しない」職場づくりを進めるケースが増えています。
まとめ:飲み会に来ない=印象が悪い時代ではない
飲み会は、昔のような「強制的なイベント」ではなく、今は自由に選べるコミュニケーションのひとつになっています。
行く・行かないで印象が決まるわけではなく、日常の仕事の姿勢や関わり方が重要です。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 昔 | 飲み会は仕事の延長・参加が当たり前 |
| 今 | 自由参加が基本・強制はNG |
| 印象 | 普段の関係性や態度が評価される |
つまり、「参加するかどうか」よりも「普段どんな人間関係を築いているか」が大切。
無理せず、自分らしい距離感で人と関わることが、現代のスマートな働き方といえるでしょう🌸
あなたも、次の飲み会を前に「本当に参加したいか」を自分の気持ちで決めてみてくださいね。


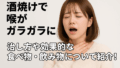
コメント