会社やサークルの「飲み会」と言えば昔から“人間関係を深める場”として大切にされてきました。しかし、近年では働き方や価値観の多様化が進み、「飲み会文化」そのものが大きく変化しています。
そんな中「新人が飲み会で全然動かない」「気が利かない」と感じたことがある先輩や上司の方も多いのではないでしょうか?
そこで今回は飲み会で動かない新人に対して、現代的な接し方・育て方・アドバイスの仕方を、実体験を交えながらわかりやすくご紹介していきます!
あくまでも個人的に感じた一例となる場合もございますので参考程度に閲覧いただけたらと思います。
なぜ新人は飲み会で動かないのか?その本当の理由
「最近の新人は全然動かない」と感じるのは、決して珍しいことではありません。しかし、その背景には“怠けている”とは別の理由があるケースが多いんです。
1️⃣ 飲み会のマナーを教わっていない
そもそも現代では入社時に「飲み会の立ち回り」を教える会社は少なくなりました。正直ほとんど0になったと言ってもいいでしょう。
かつては新人研修や先輩との交流で自然と学ぶ機会がありましたが、オンライン化やコロナ禍の影響で飲み会自体が開催されなくなった時期もあり、その文化が薄れたのが現実です。
つまり、動かないのではなくどう動けば良いかわからない、動かなきゃいけないのは昭和の時代では?というような考えの新人が多いのです。
私自身もまだ30代になったばかりの年代ですが、正直新人が動かないといけないと言う風潮の環境で働いたことがなく、店員さんを呼ぶ場合も立場関係なく呼んだら、上司のグラスが空いていたら声をかけるなど特にせず通ってきました。
2️⃣ パワハラ・セクハラへの意識が強い
そして令和の時代では、飲み会の場でも「無理に注ぐ」「強要される」という行為が問題視されています。新人の中には、「気を利かせたつもりでお酒を注いだら失礼だったらどうしよう」と戸惑っている人もいます。
3️⃣ 世代間の価値観のズレ
上司世代が「気遣い」「礼儀」として当たり前に行っていた行動も、Z世代の新人にとっては「距離感が近すぎる」「空気を読みすぎるのが疲れる」と感じられることもあります。
つまり、新人が動かない背景には、マナー・意識・世代感覚のギャップがあるのです。
昔と今の“飲み会マナー”の違いを知ろう
まずは、上司や先輩自身が「今の時代の飲み会はどう変わったのか」を理解しておくことが大切です。以下の表に、昔と今の違いをまとめました👇
| 項目 | 昔の飲み会(昭和〜平成初期) | 現代の飲み会(令和) |
|---|---|---|
| お酌・取り分け | 新人が率先して行うのが礼儀 | 強制ではなく、自主的な配慮が重視される |
| 上司との距離 | 上下関係を意識して席順や会話を気にする | フラットな関係を好む人が多い |
| お酒の飲み方 | 飲めなくても「付き合い」で飲むことが多かった | 無理に飲ませない、ソフトドリンクでもOK |
| 目的 | 上司との親睦・忠誠心の確認 | チームの理解やコミュニケーション重視 |
このように、令和の飲み会では「上下関係よりも、気遣いと快適さのバランス」が重要視されています。つまり、新人が動かない=悪いとは限らないのです🍶
社風としても飲み会は終業後なので上司部下の関係地もある程度フラットになり、下だから何事もやらないと言う風潮は少し古いのでしょう。
🤝上司・先輩として意識すべき“現代的な接し方”
では、動かない新人をどう指導すればよいのでしょうか?叱るのではなく、「行動を引き出す環境づくり」に焦点を当ててみましょう。
✅ 1. まずは新人が安心できる場をつくる
新人は、飲み会の雰囲気自体に緊張していることが多いです。そんな中で「なんで動かないの?」と言われてしまうと、ますます萎縮してしまいます。
まずは「今日はリラックスしてね」「無理に動かなくていいよ」と伝え、安心感を与えましょう。すると、自然に周囲の行動を観察し、次回から自発的に動けるようになります。
✅ 2. 具体的な行動をやさしく伝える
「気を利かせろ」という言葉よりも、「この皿を隣の席に回してくれる?」「乾杯の声かけお願いできる?」と具体的に伝えることで、新人も動きやすくなります。
✅ 3. 行動したら必ず“感謝の言葉”を伝える
「助かった!ありがとう😊」という言葉は、何よりも新人のモチベーションを高めます。動いたことを褒められる経験が、次の行動につながるのです。
✅ 4. 「気遣い」を押しつけない
現代の新人は「空気を読みすぎて疲れる」ことを嫌う傾向があります。指導する際も「これをしないと失礼」と決めつけるのではなく、「こうしておくと場がスムーズになるよ」と伝える形が理想的です。
体験談:飲み会で動かなかった新人が“場を変えた”話
ここで、実際に筆者が体験したエピソードを1つご紹介します。
ある年、私の部署に入社した新人A君。飲み会ではまったく動かず、料理を取ることもお酒を注ぐこともありませんでした。周囲は少し困惑気味…。しかし私はあえて注意せず、「次回は乾杯の音頭を頼める?」とだけ伝えました。
すると次の飲み会では、A君が自ら率先して場を盛り上げるようになったのです!後から聞くと、「最初の飲み会では勝手に動くのが怖かった」「でも任されたことで自信がついた」と話してくれました。
この経験から学んだのは、動かない新人を責めるのではなく、“動けるきっかけ”を与えることが大切ということです🌸。
新人への伝え方のコツ
新人に「もう少し動いた方がいいよ」と伝えるときも、言葉選びを間違えるとプレッシャーを与えてしまうことがあります。以下の表は、言い方の違いによる印象の変化を示したものです👇
| NGな言い方 | 好印象な言い方 |
|---|---|
| なんで動かないの?気が利かないな | これお願いしてもいい?助かるよ! |
| 昔はみんなもっと動いたよ | 今は自由だけど、こうすると場がスムーズになるよ |
| 新人なんだから当然だろ | 最初はわからないよね、一緒にやってみよう |
言葉のトーン1つで、相手の受け取り方は大きく変わります。叱るよりも、“育てるつもりで伝える”ことが大切です🌱。
飲み会は“上下関係”ではなく“信頼関係”を築く場へ
かつては「飲み会=上司への忠誠を示す場」だった時代もありましたが、今は違います。現代の飲み会は、チームの信頼関係を築き、仕事のコミュニケーションを円滑にする場です。
つまり、動く・動かないよりも、お互いが心地よく過ごせることが一番大切なんです。
上司や先輩が笑顔でいれば、新人も安心してその場に溶け込めます😊。そして、新人が小さな行動を起こしたときには、しっかり言葉で感謝を伝える――それだけで飲み会はぐっと良い空気になります。
まとめ:令和の飲み会は“教えるより育てる”姿勢で
- 新人が動かないのは「怠け」ではなく「不安」や「世代ギャップ」から
- 叱るのではなく、安心して動ける場をつくる
- 具体的な行動を優しく伝え、動いたら必ず感謝する
- 上下関係よりも信頼関係を大切にする
飲み会は、世代を超えたコミュニケーションのチャンス✨。
上司や先輩が“見守り、導く姿勢”を持てば、新人は自然と学び、行動できるようになります。
そして何より、「この人たちとまた飲みに行きたい」と思ってもらえることこそ、現代の飲み会における最高の成果です🍻。

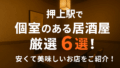
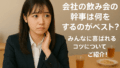
コメント